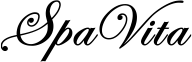011
日本のウエルネスマーケットを変える
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
「Diet&Beauty」部長/編集長
江渕 敦 氏
ウエルネス業界の3名のオピニオンリーダーが語る日本のウエルネスマーケットの未来。第3回は江渕 敦氏。昨年の日本スパ振興協会総会時の講演「メガトレンドはウエルネス〜拡大するグローバルウエルネスマーケット〜」の抄録をご紹介いたします。
日本スパ振興協会理事長のメッセージ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によりお亡くなりになった方々に謹んでお悔み申し上げますとともに、罹患された方々、不安で辛い日々を過ごされているすべての皆様にお見舞い申し上げます。
さて、昨年の当協会総会時にご講演頂いた抄録をご紹介させていただきます。それは、ウエルネス業界の3名のオピニオンリーダーから、様々なデータやご経験談を交えながらご説明いただいたもので、グローバルウエルネスサミットを通した世界の視点で日本を注目すると、日本ならではのウエルネスに気づかされ、こんな素晴らしい文化やウエルネスの慣習、地域を「J-wellness」と世界に発信していこうというような、大変興味深い内容です。
現在、新型コロナウイルスの感染拡大により、人々に見えないウィルスの脅威への不安が広がっており、医療に携わる方々のご尽力には尊敬と感謝の意を表します。このような状況で、今、自分たちにもできること、自分自身で健康でいるための行動をすべきだと思っています。
最近、「自己免疫」に改めて注目が集まっているようですが、免疫力を高めるには適度な運動、バランスの良い食事、リラックス(ストレス発散)、体を温めるなどの生活習慣が重要です。それはまさに、この講演で述べている日本のウェルネスであると思っています。
この抄録が皆さんに気づきを与え、行動に繋がってもらえたら幸いです。今は家庭内でもできる、適度な運動や、栄養管理、入浴など自宅でのウエルネスな生活を心がけていただき、新型コロナウイルスが収束した際は、ウエルネスライフの実践の場としてスパを活用していただけたらと思います。
特定非営利活動法人 日本スパ振興協会
理事長 岡田 友悟

日本のウエルネスマーケット
日本ではウエルネスという括りでの市場規模が算出されていませんが、私が各業界の数字で推計したものと経産省で保険外産業市場で算出しているのが10兆円前後なので、これがGWIで出している市場規模470兆円の中の日本にあたる部分だと類推できます。高齢化の推移は説明するまでもないですが、2060年ぐらいまでいくと、だいたい3,000万人ぐらい減ってしまう。韓国の生産年齢人数が3,500万人くらいなので、一国の生産年齢がいなくなるのに匹敵するぐらいインパクトのある数字だと思います。
健康長寿社会、高齢化社会の課題とチャンスということで、美容・健康を中心に見ていくと、生活習慣病や栄養、運動、睡眠不足、心のストレスの問題などがあります。若年女性の課題で、若年層のBMI指数が先進国の中で突出して高いということは、結婚、出産、それから、更年期といったこれからの人生においてかなり不安材料が多く、これらに対する色々なビジネス的なサポートが今後考えられていくでしょう。
「BtoBtoC」これは、経産省が推し進めようとしている、仲介者を経てサービスやプロダクツを提供していく仕組みで、例えば企業の健保組合や医療機関も含みますし、美容・健康産業のサービス施設が生かしていくこともあるかもしれません。日本の場合、自分の健康を人任せにしてきた傾向がありますので、誰かのサポート、助言、アドバイスが選択するポイントとなってきます。そうすると、機能性や安全性を担保するための認証制度が必要で、経済産業省が各業界、団体にガイドラインをつくりましょうと提案しているわけです。
次に「心の生活習慣病」「美容と健康の狭間」「生きがい」のキーワードで「人生100年時代の美容・健康ビジネス」成熟社会の多彩なライフスタイルにどう対応していくかでビジネスチャンスがあるかもしれません。
アプローチの仕方としては、安全性の担保や機能性のエビデンスにおいて医療分野との連携やBtoBtoCとIT、IoT、AI、ビックデータというもので、よりパーソナライズしていくことと、ナッジという行動変容を促すような仕掛けをしていくことです。何よりも高品質であることとパーソナライズというのがビジネスの条件になっていくでしょう。
訪日外国人についていえば、今、リピーターが60%を超え、個人旅行が増えて消費も増えています。モノからコト・体験消費へ消費傾向が移り、アジアだけでなく欧米客も増えて、日数も増えてきているということが言えます。
では、日本の魅力は何なのか。以前、日本の潜在能力について分析し、可能性を考察しているような本を読んだのですが、その中に「日本の魅力っていうのは、ガラパゴス化された長く閉ざされたところがグローバル化の波を受けて、本来の日本の姿が垣間見れるということが魅力だ」というようなことが書いてあったと思います。情報が少なかったからこその高まる期待というのがあると思います。あとは、清潔さ、勤勉さ、正確さ、やさしさ、それから、何より信頼できるという意味で日本の美容・健康サービスとかプロダクツには非常に憧れがあると思います。

J-WELLNESS
ウエルネス。ただ、日本人はそれに気付かなかったという話なのです。ドイツのフライブルク大学医学部教授のナウマン氏とイタリアのアバノ・モンテグロット温泉ホテル協会の元会長のマッシモ氏、お二方が来日されインタビューをD&Bに掲載しています。ナウマン先生は、「心の健康資源としての温泉地に魅力がある」とおっしゃっていました。また、日本の町の清潔さ、交通機関の正確さ、人々の礼儀正しさ、温泉、職人の多彩さということを非常に評価されていました。マッシモさんは、「日本人は日本の豊かさに気付いていない」という言い方をされています。それはお金の豊かさを指しているわけではなく、量から質の転換の時に日本はもっと注目されていくということです。マッシモさんは50数回も来日していて、大分県竹田市の温泉に行ったときには畳を縫う作業場に半日座って見ていたとか、山中温泉では機織りをじーっと何時間も見ていたという話をされていました。彼らの言葉の中に日本人が気付かないウエルネスというのがあるような気がしています。
今日どうしても言いたかったのは、「J-WELLNESS」と、我々で言ってしまいませんか、ということです。韓国は「K-BEAUTY」を国家戦略として産業を発展させていますが、今は、高齢化に対する様々な施策やプログラムを「K-WELL」として戦略的に外へ出していこうという動きをしているわけです。
ウエルネスは欧米の医学からの概念なので日本人には理解しがたいのかもしれませんが、「日本のもともとあるものだからかもしれない。自覚できないからビジネス化できてない。ビジネス化できてないからガラパゴスになっている。だけど、そこが魅力ある。外国人にとってみると、日本のウエルネスってそういうことだと思っている節もどうやらありそう。日本人はそこに気付かないけど、やっぱり日本はそこが魅力なんだ。」というようなことです。
定義づけしようとするとなかなか進まないので、とにかく外に対して「J-WELLNESS」と発信する、それが海外からの期待にも応えるということではないでしょうか。
今後、標準的医療からパーソナルな医療、スマート社会、ソサエティー5.0などをみても、おそらくウエルネスもパーソナルな方向が求められていくということが一つ言えるでしょう。そのヒントが先ほどのインタビューの中にあるとしたら、例えば、町並みのそぞろ歩きや、そこで出会う人や、作為のないおもてなしというような、パーソナルな滞在の中に何かあるかもしれない、それを追及し続けることが解を見出すのではないかというような気がしています。また、日本にはいろんな要素、コンテンツがたくさんあるので、各々が連携してウェルネスビジネスとして発展させて消費者に近づいていくということが、今、肝心ではないかと感じています。

江渕 敦(えぶち あつし)
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社「DIET&BEAUTY」部長/編集長。総合広告会社勤務を経て、健康産業新聞社(株)(現 インフォーマ マーケッツ ジャパン(株))入社、企画室長を経て現職。美容・健康分野の展示会「ダイエット&ビューティーフェア」「アンチエイジングジャパン」「スパ&ウエルネスジャパン」や「スパシンポジウム」「CRYSTAL Award」「SPA&Wellness Week」実施。また、地域の美容・健康商材の「Japan Made Beauty Award」「Japan Made Beauty研究会」主宰。講演は健康博覧会、ヘルスケアIT、Cosmoprof ASIA(香港)、沖縄、新潟、徳島県等で多数。

岡田 友悟(おかだ ともあき)
特定非営利活動法人 日本スパ振興協会 理事長╱一般社団法人 スパ&ウエルネスウィーク 代表理事╱公益社団法人 日本サウナ・スパ協会 諮問委員╱沖縄県エステティック・スパ協同組合 顧問╱一般財団法人 国際指圧普及協会 理事╱国立大学法人 琉球大学 非常勤講師。スパ施設に化粧品・トイレタリー製品の販売を行う商社にて、多くの施設の立ち上げにかかわる。幅広くスパ、温泉、温浴、サウナに関する活動を行う。